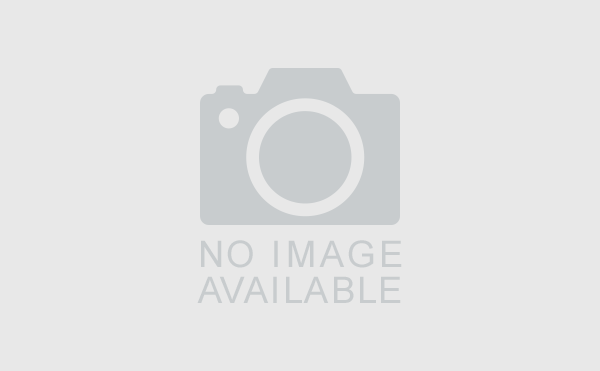【寄稿】『中野・中西家と光太郎』から想うこと 石川さなえ
中野・生活者ネットワークのサポーター石川さなえさんから、中野区で活動した画家・中西利雄さんについての寄稿が届きましたので以下、ご紹介します。
「過日は、活動報告ならびに菜の花通信を送付くださいましてありがとうございました。
最近の異常気象による災害や物価の高騰、国際的社会規範の乱れ、各国のリーダーによる暴挙、とても不安です。地球の平和や秩序を願うばかりです。
さて、最近読んだ文献に生活者ネットワークの活動と重なる部分があり、是非お伝えしたくペンを取る次第です。 本のタイトルは『中野・中西家と光太郎』、勝畑耕一著、小山弘明監修、文治堂書店出版です。著書には昭和初期に建てられたアトリエと居宅、そこで活動した2人の芸術家が紹介されています。
家主の名は中西利雄氏、大正から昭和にかけて日本の水彩画の発展に寄与した草分け的存在です。彼は明治の後半に旧京橋区で生を受け、旧牛込区で学生生活を送り、震災を機に中野の桃園地区へ移り住みます。やがて始まる大戦では、一旦は神奈川県の沢井村へ疎開します。時代に翻弄されながらも、当時の画家や文豪との絆を保ち、疎開先で戦争を乗り切る様子が伝わります。
若い時の中西氏は、ヨーロッパ留学でその才気に磨きが掛かり、当時の芸術家たちに新たな息吹を吹き込みます。所帯を持ち、戦後は再び中野へ戻りますが、その僅か2年後に人生を閉じます。後の世にも、その精神は周囲の人々に深く根付いた事は言うまでもありません。
著書の後半は、2人目の芸術家、高村光太郎氏について、戦火の東京を離れた光太郎が東北の花巻市へ移り住むところから始まります。親交のあった著名な文化人との交流が綴られます。
やがて、周囲の協力もあり未完の大作を抱え中野のアトリエへ移り住んだのは1952年の秋でした。晩年の光太郎が、中西氏の妻や子どもたちとのほのぼのとした様子が描写されています。光太郎は1956年4月に息を引き取ります。
雑駁な説明でしたが、ここからが本題です。
生活者ネットワークの流域治水の調査が、現代社会の中で重要な位置づけにあることは周知の通りです
その調査の対象地域にはこの本と重なるところが多々あります。
以下は本文からの引用です。
「震災後に中野区・桃園へ」
「武蔵野の中央に位置するため中野という地名が生まれたといいます。区内には妙正寺川、江古田川、中野川 (現在は暗渠となり桃園川緑道)、神田川が流れ縄文弥生時代の遺跡が区内に14カ所確認されています。遠い昔から人々は農耕生活に適した河の沿岸に居を構えていたのです。十世紀の文献には「武蔵中野の原」という語もあり、平安時代に生まれた群がみられます。今も地図上にある中野・新井・沼袋・鷺宮・江古田・高田の名がみられます。」(『中野・中西家と光太郎』:勝畑耕一, p.14)
さて、文中の中野の郷土・歴史の解説を読み解き、生活者ネットの活動を照らし合わせると、流域治水調査の対象が中野の地であるならば、水質や防災ばかりでなく、川の歴史や風土とそこに生きてきた人々の足跡を知ることで、市民の関心が高まり参加する動機付けにもなり得るのではないでしょうか。地形や歴史を学びながらの活動にも新たな発見が期待できるのではないでしょうか。 以前、生活者ネットのスタッフの方が会議の時に「政治は台所の水とつながっている」と、盛んに言っていた事を思い出します。中野の河川の歴史、郷土・地形の変遷を学びながらの活動には幅が出で、更にこの本の価値を知りうると思いました。
もう一点ばかり、是非お伝えしたい箇所があります。27頁に掲載されている水彩画です。そこには、東中野駅(新聞小説『帰郷』より)と表題があります。
疎開から戻り、再び中野を拠点に活動が始まった翌年1948年の挿絵です。終戦直後の東中野の駅舎は、背景は変わったものの、今も当時のままに映ります
挿絵を見て、十数年以上も前のある行政の会議をふと思い出しました。近隣の方の訴えです「年齢が嵩み、足腰が弱って歩行がままならない、連れ合いを支えるのにも階段は大変です。東口側にもエレベーター等の設置があれば外出がもっと楽になります。不便を感じる住人のために、どうかそれなりの予算をつけてください」この言葉を記憶してからどのくらいの月日が経ったのでしょう。
近年、中野駅周辺は都心さながら新たなビルが乱立し、サンプラザや新庁舎の建設等々、開発計画ばかりが目立ちます。ユニバーサルデザインとは名ばかりで、今の中野駅周辺は高齢者や障碍を抱えている人に果たして優しいでしょうか?
本当に必要なところに目を置き、僅かな声に耳を傾け、困っている市民のために細やかな仕事をすることが、地方自治体の役割だと思っています。
著書からは中野の歴史を垣間見れたことも然り、中西利雄氏や高村光太郎氏を支える人々が自分の利益のみを考えず先を見据えた行動ということに気付かされました。生き方に共鳴する人たちが集まったのだと思います。
最近、このアトリエに関する展覧会や講演会が開催されました。
アトリエの存在と中野の郷土、生活者ネットワークの活動が複合的な動きになると嬉しく存じます。
石川さなえ
注:『中野・中西家と光太郎』を知ったのは、昨年11月に開催された「中野を描いた画家たちのアトリエ展Ⅱ」でした。展覧会を主催した中野たてもの応援団は、中野区内にある戦前戦後活躍した芸術家の一人としてスポットを当て、作品の掘り起こしとアトリエの保存活動をしています。2月15日には茨木県近代美術館主席学芸員山口和子氏を招いて「中西利雄の人と作品」と題した講演会が開催されました。」
(詳細はたてもの応援団のホームページ参照)『中西利雄 人と作品』 講師:茨城県近代美術館首席学芸員 山口和子氏 2025年2月15日(土)14:00~ | 中野たてもの応援団
石川さなえさんの寄稿に感謝しております。中野・生活者ネットワークは、まちづくりには地域の歴史、地理、文化的背景の理解と考慮が大切と考えております。ホームページでも中野区各地域を紹介していきたいと考えています。
中野・生活者ネットワーク