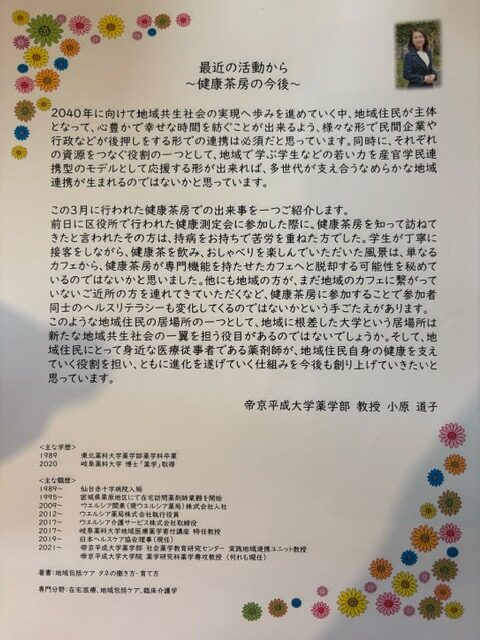「健康と薬学のお話」 小原道子さん (帝京平成大学教授)
学習会報告
4月20日(日)13:30~15:30:中野区新井区民活動センターにて
帝京平成大学では、「健康茶房」というユニークなイベントを開催しています。「健康茶房」は、薬学部教授の小原道子先生が推進する地域連携活動の1つで、参加者は健康茶を試飲しながら、学生と交流、薬学や健康法、フレイル予防体操などを学びます。今回は、小原先生に「健康と薬学」をテーマにお話を伺いました。以下、報告です。
時代と共に変化する薬剤師の役割
「薬剤師」とは、どのような仕事をする人でしょうか。わたしたちの多くは、病院や、薬局で医師の出す処方箋に従って薬を調剤する人と考えがちではないでしょうか。薬剤師の育成は、昔は主に薬の作り方が中心で、就職先は薬局、病院、民間企業と限られていました。小原先生は、薬剤師に求められる役割は時代とともに変化してきた、薬剤師は人びとがウェルビーイング(ご機嫌な時間=幸福)であるために健康な時から関わる一番身近な医療職の医療関係者と言います。また、医療は内科、外科……と分かれているのに対して、薬剤師は全科をカバーし、扱う薬の種類・組み合わせも幅広い対応を要します。(例えば痛みに効く薬でも即効性がある、眠くならない、胃に負担がすくない、生理痛に効くなどと違いがあるそうです。)仕事の種類は、医療のサポートをするほか、災害対応、研究、病棟調剤、介護相談、在宅訪問、生活支援、セルフメディケーション、マネジメントまで多岐にわたります。(例えば、災害対応では、小原先生は2024年1月の能登半島地震被災地の避難所のトイレの清掃ボランティアをしながら汚れにくい掃除法を啓発されたそうです。)
地域社会の課題は、介護者の増加、地域格差の拡大、核家族や高齢独居者の増加(30年前は3世帯同居が人口の40%だったが今は8%しかいない)などで社会的に孤立するひとが増えています。2025年を境に外来患者数は減少し、2040年には訪問診療が増加すると予測されています。現在、薬剤師には人との交流、AI、国際化、地域連携が求められています。
転機となった農山村の訪問薬剤師
小原先生は、出身地の仙台で薬剤師になって以来、さまざまな地域の困難な課題に取り組んできました。薬剤師としての小原先生の転機は、宮城県栗原地区で患者さんのところにお薬をもって訪問する「訪問薬剤師」になった時でした。当初は、医師、看護師と一緒に患者さんのお宅を回ってください、と言われても実際に何をしてよいか想像もつかなかったそうです。最初の訪問先は、人里離れた広い茅葺屋根の農家で日中は独居状態の全盲のおばあさんでした。医師が薬を処方しても一人では適切な薬の服用がままならない状況。さまざまな試行錯誤の末、三つの牛乳パックに大きさの異なる鈴をつけたことで、朝・昼・夕の薬を間違わずに服用できるようになったそうです。このような創意工夫は、患者さんの暮らしを直に接してこそできることです。
家族のような出会いもありました。子どもたちが独立して二人暮らしになった高齢のご夫婦は、親のように接してと希望されたそうです。そこでお二人を訪問したときは「ただいま」「おかえり」とあいさつを交わしていたそうです。お二人にはお薬とともに明るい気持ちを届けていたといえます。訪問薬剤師の仕事を通して、沢山の経験をされて、地域連携という新しい可能性と役割を見出されたのでしょう。
活躍の場は、大型ドラッグストアを運営する企業に勤務、岐阜薬科大学特任教授へと広がり、自治体とともに地域包括支援センター設立、過疎の小さな集落に薬が届くようにモバイルファーマシー(移動薬局)の研究、医療過疎地域の健康測定会を立ち上げるなど、地域ごとのニーズに合わせて新しい薬剤師の役割を創設されてきました。2020年には経験をもとに論文を執筆、博士「薬学」を取得、2021年には現職の帝京平成大学薬学部の教授となり中野が活躍の場になりました。
学生とともに地域連携を実践
小原先生が帝京平成大学に就任された2021年はコロナ禍の真っ只中。学生たちは、三密(密接・密集・密閉)回避を求められて、地域連携を学ぶことが難しい状況だったそうです。
そうした中で小原先生は学生たちと「地域連携サークル」(後に地域連携部:大学公式の部活動)を立ち上げ、薬育活動の普及や地域や町会の人たちが行う見守り活動に参加、新たに昨年度からは「健康茶房」を始めました。「健康茶房」には中野区、区民、製薬会社、健康食品、健康茶メーカーが協力しています。また、参加する高齢者は健康茶の試飲だけでなく、すこやかな暮らしの情報をえるとともに、提供されるお茶や健康食品のモニターでもあります。テーブルに設置してあるタブレットでお茶の効能を調べながら、タブレット操作も学べるように工夫されています。参加者は学生との交流を楽しみ、学生は経験を通してコミュニケーション力を高めているそうです。このように「健康茶房」は産・官・学・民の地域連携の好循環を作りだしています。
健康茶の試飲
小原先生のお話の間に4種類の健康茶を試飲させていただきました。
トウモロコシ茶(桑の葉・杜仲茶入り:抗酸化作用、血糖値を下げるなど)、ごぼう茶(香ばしく、便秘を改善)、花通茶(かつうちゃ:烏龍茶をベースにハッカ入り:すっきりする)、活元茶(かつげんちゃ:紅茶をベースに高麗人参、霊芝など入り:元気がでる)
お話からは、小原先生が日々の目の前にある仕事に向き合い研鑽を重ねながら薬学・薬剤師の役割と可能性を切り開かれ、その結果として「健康茶房」をはじめとする現在の活動に繋がっていることが分かりました。まさに、ウェルビーイング(ご機嫌な時間:幸福)を分けていただきました。 (報告:加藤まさみ)
参加者の感想
参加者からさまざまな感想や質疑がありました。以下、参加者の感想の抜粋です。
- 先生を中心としてのご活躍のお話はとてもたのもしく、ありがたいなあと思いました。身近な場所でのお話がある時は又参加したいと思います。健康で楽しい日々が送れるよう意識をしっかり持って暮らしていきたいと思います。
- 若い世代が活躍してくれることにより多世代の活性化につながると思います。高齢者は若者を好みます! 学生たちのガッツに期待しています。
- 有意義なお話に引き込まれました。ロキソニンSに5種類もあるのにはびっくりしましたし、勉強になりました。ありがとうございました。
- 素晴らしい会‼ 日毎心にかけていたことを解決して下さって本当にありがとうございました。地域に貢献してくださる活動に大変心強さを感じ、中野区に住んでよかった‼ と実感させて頂けた会でした‼ よくお勉強なさって最高のお話しでした。
- 薬剤師さんや薬学の方が地域に深くかかわって活動されていることを初めて知り、とても素晴らしいことと思います。若い学生さん達が生き生きと前向きに活動しているのはとても嬉しいです。薬のことはほとんどお医者さんに処方されるまま飲んでいることが多いが、消費者としてもっと薬を知ることも必要かと思う。薬剤師さんのお話をもっと聞いてみたいと思いました。
- スライドとお話しだと見のがし、聞きもれがあるのでレジュメがあるともっと良くわかったしあとあとまでレジュメをみて学べると思いました。先生のご活躍すばらしい。これからももっともっとご活躍を祈ります。「花通茶」はハッカがきいてて飲みやすく、おいしかったです。良いお話し有難うございました。以上。
学習会には26名の参加があり、11名の方から感想をいただきました。次回はレジュメを用意します。(記録:田辺雪子)
次回「健康茶房」は6月7日 10時~11時45分時 帝京平成大学中野キャンパス1Fこもれびの予定です。
「健康茶房」については、https://hoitto-hc.com/17947/ と https://hoitto-hc.com/18216/ をご参照ください。
小原先生の著書:『地域包括ケア 種の蒔き方・育て方』:評言社MIL新書004 2021年3月
小原先生がパーソナリティを務めるラジオ番組:「ビタミンラジオラジオ」NIKKEI第1 毎月第1・第2金曜日 17:30~17:50 同週土曜日 17:40~18:00(再放送)